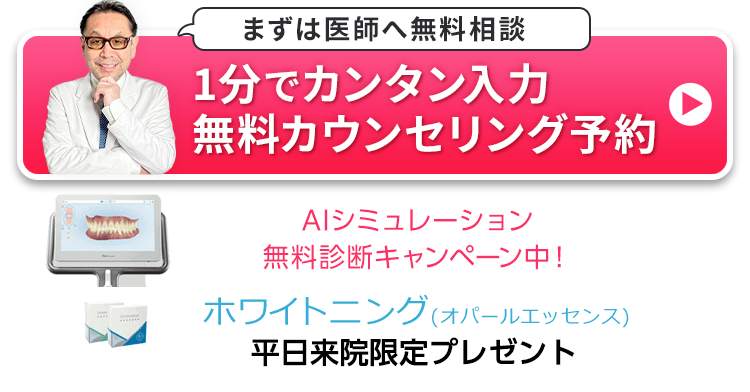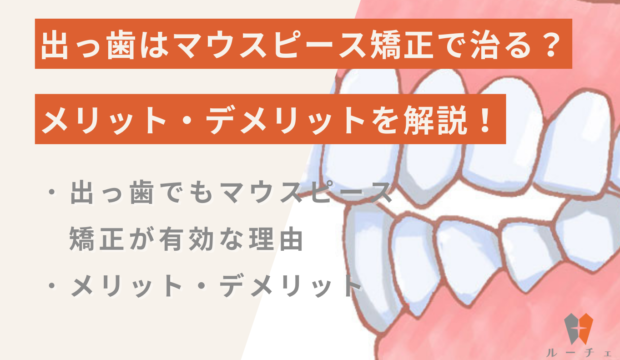目次はこちら
マウスピース矯正(インビザライン)は医療費控除の対象になる?
結論からお伝えすると、マウスピース矯正(インビザラインを含む)は条件を満たせば医療費控除の対象になります。
矯正治療というと美容目的と誤解されがちですが、「噛み合わせの改善」、「発音障害の解消」など、治療を目的としたケースでは医療費控除が適用されます。
とくに成人の方が受けるマウスピース矯正は高額になるケースが多く、費用の一部が還付される医療費控除を利用することで、経済的負担を大きく軽減できます。
ここでは、医療費控除の対象範囲や申請方法、計算例などを詳しくご紹介します。
医療費控除の対象になるもの
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得控除を受けられる制度です。
矯正治療において、以下のような費用が医療費控除の対象となります。
対象となる費用の例
- マウスピース矯正の治療費(インビザラインなど)
- 初診料・診察料・検査費用
- 矯正装置の作製・調整費
- 通院にかかった交通費(公共交通機関を利用した場合)
- 投薬料、歯のクリーニング(医師が治療の一環として必要と判断した場合)
一方、以下のような費用は対象外となります。
対象外となる費用の例
- 美容目的の矯正治療(例:見た目の改善のみが目的の場合)
- 自家用車での通院時のガソリン代や駐車場代
- ホワイトニングや審美治療(ラミネートベニアなど)
「治療目的」であることが前提となるため、医師の診断書や治療計画書などを保管しておくと安心です。
医療費控除の申請方法
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。
以下では、申請に必要なものやタイミング、注意点について解説します。
必要なもの
- 源泉徴収票(会社員の場合)
- 医療費控除の明細書(医療費通知を活用可能)
- 支払った治療費の領収書(明細作成の裏付けとして保管)
- 通院にかかった交通費の記録(日時・交通手段・金額など)
- マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
マウスピース矯正にかかった費用も、これらの書類に基づいて申請できます。
明細書に記載する金額が、実際の支払い金額と一致しているかを確認しましょう。
申請のタイミング
医療費控除の申請は、対象となる医療費を支払った年の翌年から行えます。
たとえば、2024年中に矯正治療費を支払った場合、2025年2月16日〜3月15日の確定申告期間に申請します。
e-Tax(国税庁の電子申告システム)を使えば、自宅から簡単に申告できます。
マイナンバーカードとスマートフォンを使った申告に対応しているほか、事前に税務署でIDとパスワードを発行してもらえば、マイナンバーカードがなくても申告が可能です。
申請期限
医療費控除の申請期限は、申告対象の翌年から5年間です。
つまり、2024年分の医療費控除は、2029年まで申請可能です。
期限を過ぎると控除が受けられなくなるため、忘れずに手続きを行いましょう。
申請の注意点
- 領収書は提出不要ですが、5年間の保管義務があります。
- 分割払いやデンタルローンを利用している場合、「実際に支払った年」が対象となります(後述)。
- 医療費控除は、世帯全体で合算可能です(後述)。
医療費控除でいくら戻ってくる? 計算シミュレーション

では、実際にどれくらいの金額が戻ってくるのでしょうか?以下はモデルケースを使ったシミュレーションです。
モデルケース
- 年収:500万円
- 矯正費用:80万円(うち30万円をその年に支払い)
- 他の医療費:10万円(家族分含む)
医療費控除の対象額は、支払った医療費の合計から「保険金などで補填される金額」と「10万円または所得の5%(いずれか少ない方)」を差し引いた金額です。
このケースでは、以下のように計算できます。
- 控除対象額 = (30万円+10万円)− 10万円 = 30万円
- 所得税の還付額(目安)= 控除額 × 所得税率(例:10%)= 30万円 × 10% = 3万円
実際の還付額には、住民税の軽減分も含まれるため、さらに多くなる場合もあります。
分割払いやデンタルローンを利用した場合はどうなる?
マウスピース矯正は高額なため、分割払いやデンタルローンを利用する方も少なくありません。これらの支払い形態であっても、医療費控除の対象になる可能性があります。
ただし、「実際に支払った年」の費用のみが控除対象です。
たとえば、2024年に契約し、毎月2万円ずつ支払っている場合、2024年の医療費控除の対象となるのは、実際に支払った金額(例:2万円×12か月=24万円)のみです。
また、デンタルローンの金利や手数料は医療費控除の対象外です。
ローン会社からの明細をもとに、治療費として実際に支払った部分だけを記録するようにしましょう。
矯正治療が年をまたぐ場合の手続き方法

矯正治療は数年にわたる長期治療になることが多く、支払いが年をまたぐこともしばしばあります。
このような場合、年度ごとに分けて医療費控除を申請する必要があります。
ポイント1:支払った年で区切って申告する
たとえば、2024年に40万円、2025年に40万円支払った場合、それぞれの年に分けて医療費控除を申請する必要があります。
全額をまとめて翌年に申告することはできません。
ポイント2:治療開始年が対象ではない
医療費控除の対象となるのは、実際に「治療費を支払った年」です。
「契約した年」「治療開始年」ではなく、「支払いが発生した年」で計算します。
ポイント3:申告漏れに注意
年をまたいでの申告は忘れてしまいがちです。
「まとめて申告しよう」と思っていたら、過去分の申告期限が切れていた……ということのないよう、こまめに申請するか、5年以内に遡って申告しましょう。
そもそも医療費控除とは? 目的やメリットについて
医療費控除とは、年間に支払った医療費が一定の金額を超えた場合に、所得控除を受けられる制度です。
これは、病気やけがなどによって多額の医療費を支払った方の経済的負担を軽減するための仕組みです。
医療費控除の目的
日本では、公的医療保険制度によって多くの医療費が補助されますが、それでも矯正治療や自由診療などは高額になるケースがあります。
そうした支出に対して、税金面で一定の救済を受けられるのが医療費控除です。
医療費控除を受けるメリット
- 所得税・住民税の負担が軽減される
- 高額な自由診療(矯正やインプラントなど)にも適用可能
- 家族全員の医療費を合算できるため、対象額が大きくなる可能性がある
矯正治療の費用は数十万円から百万円を超えることもあるため、控除の有無で実質的な支出額に大きな差が出ます。
医療費控除の下限と上限について
医療費控除には、「下限」と「上限」に相当する基準があります。
控除の下限
医療費控除の対象になるのは、以下の金額を超えた部分です。
年間の医療費総額 − 保険金などの補填額 − 10万円(または所得の5%、いずれか少ない方)
たとえば、所得が300万円の方の場合、5%は15万円なので「10万円」が基準になります。
控除の上限
控除対象の上限は「200万円」です。
たとえ1年間に300万円以上の医療費を支払っても、控除できるのは最大200万円分までです。
保険金などを受け取った場合
医療費の一部が医療保険や共済から補填された場合、その補填額は医療費総額から差し引く必要があります。
例:
- 治療費:80万円
- 医療保険で受け取った金額:20万円
- 実質的な医療費控除の対象:80万円 − 20万円 = 60万円
医療費控除の申請方法(領収書は提出不要?保管期間は?)
確定申告で医療費控除を申請する際、2022年分以降は領収書の提出は不要となりました。
ただし、一定のルールがあります。
提出不要だが「明細書」が必要
税務署へ提出するのは、「医療費控除の明細書」です。そこには以下の情報を記載します。
- 医療機関名
- 治療内容
- 支払った金額
- 支払年月日
領収書は5年間保管
明細書の内容を裏付けるため、医療機関から受け取った領収書やレシートは「5年間の保管義務」があります。
税務署から求められた場合に提出できるようにしておきましょう。
医療費通知の活用
健康保険組合から届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」をそのまま明細書として利用することも可能です。
ただし、自由診療や矯正治療など、保険外診療の分は載っていないため、別途記録が必要です。
よくある質問Q&A

夫の扶養に入っている妻でも申請できる?
はい、できます。
ただし、扶養に入っている妻が申告するのではなく、「生計を一にしている配偶者(夫)」が、妻の医療費を合算して申告する形が一般的です。
逆に、パート収入などで一定の所得がある妻自身が確定申告を行う場合は、自分名義で申請も可能です。
家計の状況に応じて選びましょう。
家族の分も合算できる?
はい、同一生計であれば、家族全員の医療費を合算して医療費控除を申請できます。
合算できる家族の例:
- 配偶者
- 子ども(未成年、学生など)
- 両親(同居または仕送りで生活支援している場合)
たとえば、自分の矯正治療費と、子どもの通院費を合算して一括で申告することができます。
ることができます。
市販薬や健康診断は対象?
基本的に市販薬や健康診断は医療費控除の対象外ですが、以下の条件を満たす場合は控除対象になります。
- 市販薬:スイッチOTC医薬品を年間12,000円以上購入した場合、「セルフメディケーション税制」が利用可能
- 健康診断:異常が見つかり、引き続き治療に至った場合は対象になることも
※セルフメディケーション税制と医療費控除はどちらか一方のみ選択可能です。
※スイッチOTC医薬品とは、もともと病院でしか使えなかった処方薬の成分が、安全性などが確認されたうえで、市販薬として薬局で買えるようになったものです。
医療費通知が届かない場合は?
会社員や公務員の場合、年明けに健康保険組合から「医療費のお知らせ(通知)」が届くのが一般的ですが、届かない場合は、医療機関ごとの領収書をもとに「明細書」を自作すれば問題ありません。
特に自由診療(矯正治療など)は医療費通知には記載されないため、領収書はきちんと保管しておくことが重要です。
医療費控除の明細書の書き方
明細書は以下のような様式になっています。
| 医療を受けた人 | 医療機関名 | 治療内容 | 支払金額 | 支払年月日 |
| 山田 太郎 | ○○歯科 | 矯正治療 | 300,000円 | 2024年 5月 |
このように、治療を受けた人ごと、医療機関ごとに記載します。
支払日が異なる場合は、分けて記載するか「合算」としてもかまいませんが、明細性が保たれるように記録しましょう。
まとめ

マウスピース矯正は「治療目的」であれば、医療費控除の対象になります。特に高額になる矯正治療では、控除によって所得税・住民税の軽減が期待でき、経済的なメリットは大きいです。
確定申告に不慣れな方も、e-Taxや医療費通知の活用でスムーズに申請できるようになっています。
支払い方法が分割でも、年をまたいでも、実際に支払った年で正しく記録・申告すれば控除を受けられます。
大切なのは、治療費の領収書や契約内容をしっかり保管し、毎年の確定申告時期にあわせて準備することです。
少しの手間で大きな還付を受けられるこの制度を賢く活用しましょう。
投稿・監修者プロフィール
- このブログでは、患者様や一般の方々が歯科医療に関する理解を深め、健康な歯と口腔を保つための情報を提供しています。新しい治療法や予防のためのケア方法、口腔衛生に関するヒントなど、幅広いトピックにわたって記事を更新いたします。
最新の投稿
マウスピース矯正2025年11月10日マウスピース矯正ブランドの選び方|おすすめポイントと比較まとめ
マウスピース矯正2025年11月3日マウスピース矯正は高校生に向いている?費用・期間・注意点まとめ
マウスピース矯正2025年10月27日マウスピース矯正と筋トレの両立|外すべき?つけたままで大丈夫?
マウスピース矯正2025年10月20日マウスピース矯正はいつ慣れる?|滑舌や痛みの変化を徹底解説